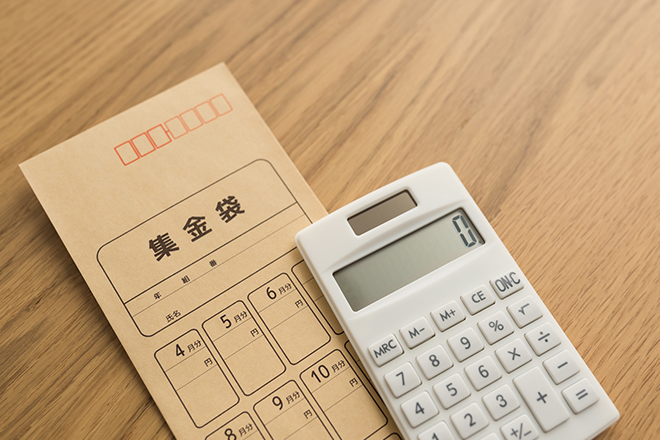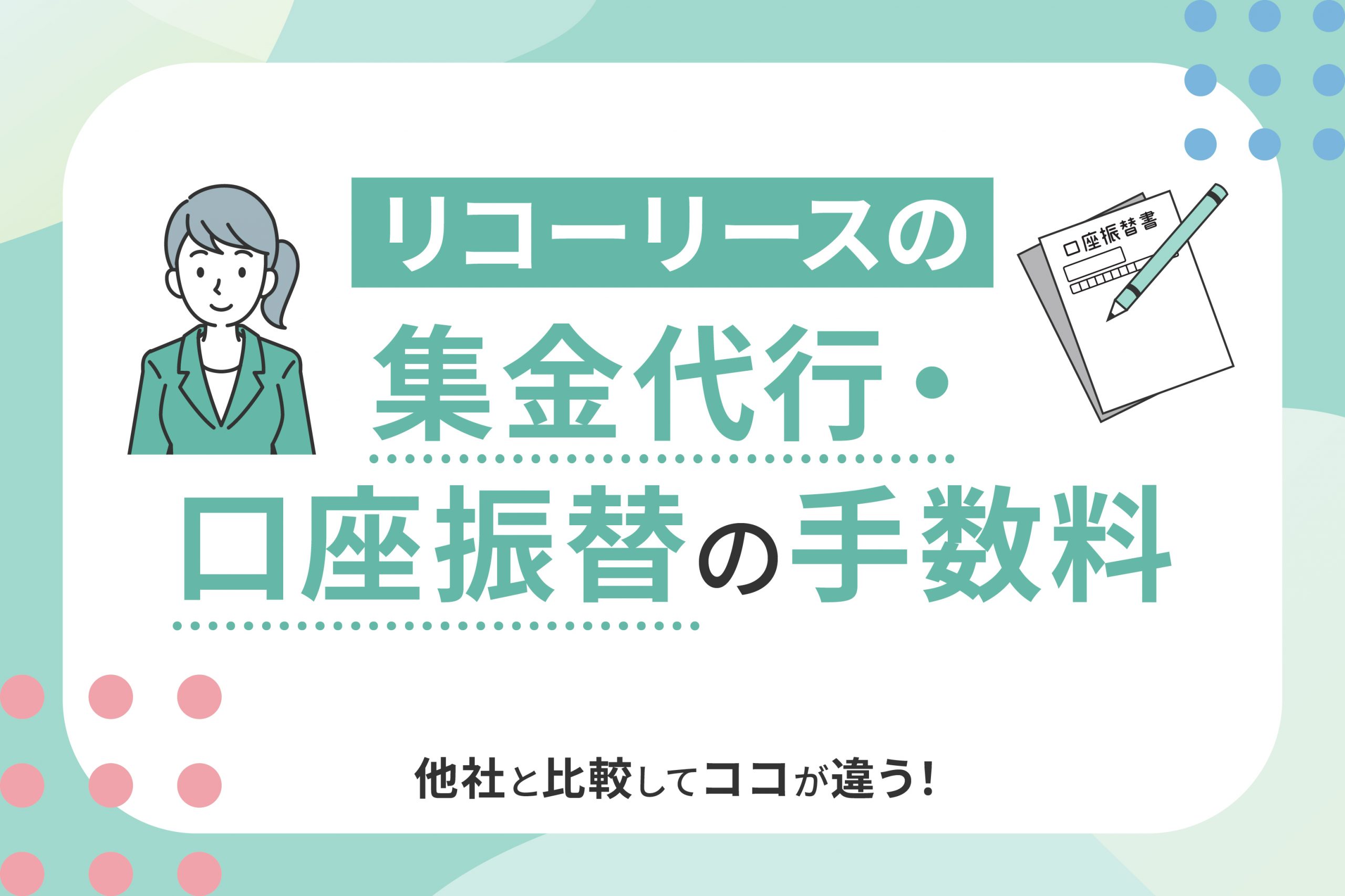医療費未収金にはどのように対策する?主な原因と回収方法・予防策を紹介
![]() 2025.10.10
2025.10.10
 " alt="医療費未収金にはどのように対策する?主な原因と回収方法・予防策を紹介">
" alt="医療費未収金にはどのように対策する?主な原因と回収方法・予防策を紹介">
医療費の未収金は、医療機関の経営を圧迫する問題のひとつです。その原因には、緊急搬送時の保険証不携帯や患者の経済的困窮、外国人患者の増加など、さまざまなものがあります。なかには、未収金への対策に頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、医療費の未収金が発生する原因から具体的な予防策、効果的な回収方法までを紹介します。予防策も併せて見ていくため、状況に応じて適切に対処し、可能な限り未収金を削減しましょう。
「見積依頼」も素早く対応!
お気軽にご相談ください
目次
医療費の未収金へ対策が必要な理由

医療費の未収金は、医療機関の経営に影響する大きな問題のひとつです。未収金が増加すると、医療機器の更新や職員への給与支払いに支障をきたす恐れがあります。さらに、回収業務に多くの人員と時間を割く必要が生じ、本来の医療サービスの質にも影響を及ぼしかねません。
そのため、もし未収金が発生した場合は速やかに回収する必要があります。放置していると未収金の金額が大きくなり、回収自体が難しくなりかねないためです。
併せて、未収金が発生しないように事前に対策することも欠かせません。未収金が発生しなければ督促を含めた回収業務にリソースを割り当てる必要はなく、その分本来の業務に集中できます。
医療費未収金が発生する3つの主要原因とその特徴

医療費の未収金対策を考える際は、発生原因を正確に把握することが重要です。緊急搬送時の特殊な状況や患者の経済的な事情、外国人患者の受診など、さまざまな原因があります。
ここでは、医療費の未収金が発生する3つの主要な原因について詳しく見ていきましょう。
緊急入院に伴う資格確認書・所持金の不携帯
急病や負傷による救急搬送・緊急入院時における資格確認書の不携帯や所持金不足は、医療費の未収金が発生する原因のひとつです。救急搬送された患者が財布を持っていないケースは十分に考えられるでしょう。
治療後を後日支払うことで合意していたとしても、なかなか支払ってもらえず未収金が発生するケースもあります。また、患者が意識不明の状態で搬送され、身元確認が困難な状況も発生しがちです。医療機関は患者の回復を待って請求しますが、経済的困難などの理由でそのまま未収金になることもあります。
患者の経済的困窮
患者が経済的に困窮していて医療費が支払えないことも、未収金が発生する原因のひとつです。健康保険が適用されても治療内容によってはある程度の負担が発生するため、支払いが困難になる場合があります。
例えば、慢性疾患の治療で入退院を繰り返し、未収金が雪だるま式に増加するケースもあるでしょう。また、認知機能の低下により、患者本人が未払いを認識していないこともあります。
未収金を防ぐには、経済的に困窮している患者に対して医療ソーシャルワーカーと連携して支援するなどの対策が必要です。
外国人患者による未納
外国人患者による医療費未払いも、医療機関にとって深刻な課題です。厚生労働省が2025年に発表した「令和6年度 医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」では、2024年9月1日~30日に外国人患者の受入実績がある2,890病院において、470病院(16.3%)で外国人患者による未収金が発生したという結果でした。
未収金の発生原因として、言語の違いによって説明が十分に伝わらず、支払いを認識していないケースが考えられます。また、旅行保険に加入していない旅行者の場合は全額自己負担になるため、支払えないこともありえるでしょう。
現金の持ち合わせがなかったりクレジットカードの利用限度額を超えたりするなど、支払い手段が問題になる場合もあります。
参考:令和6年度「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」の結果
「見積依頼」も素早く対応!
お気軽にご相談ください
医療費の未収金が発生した後の対策
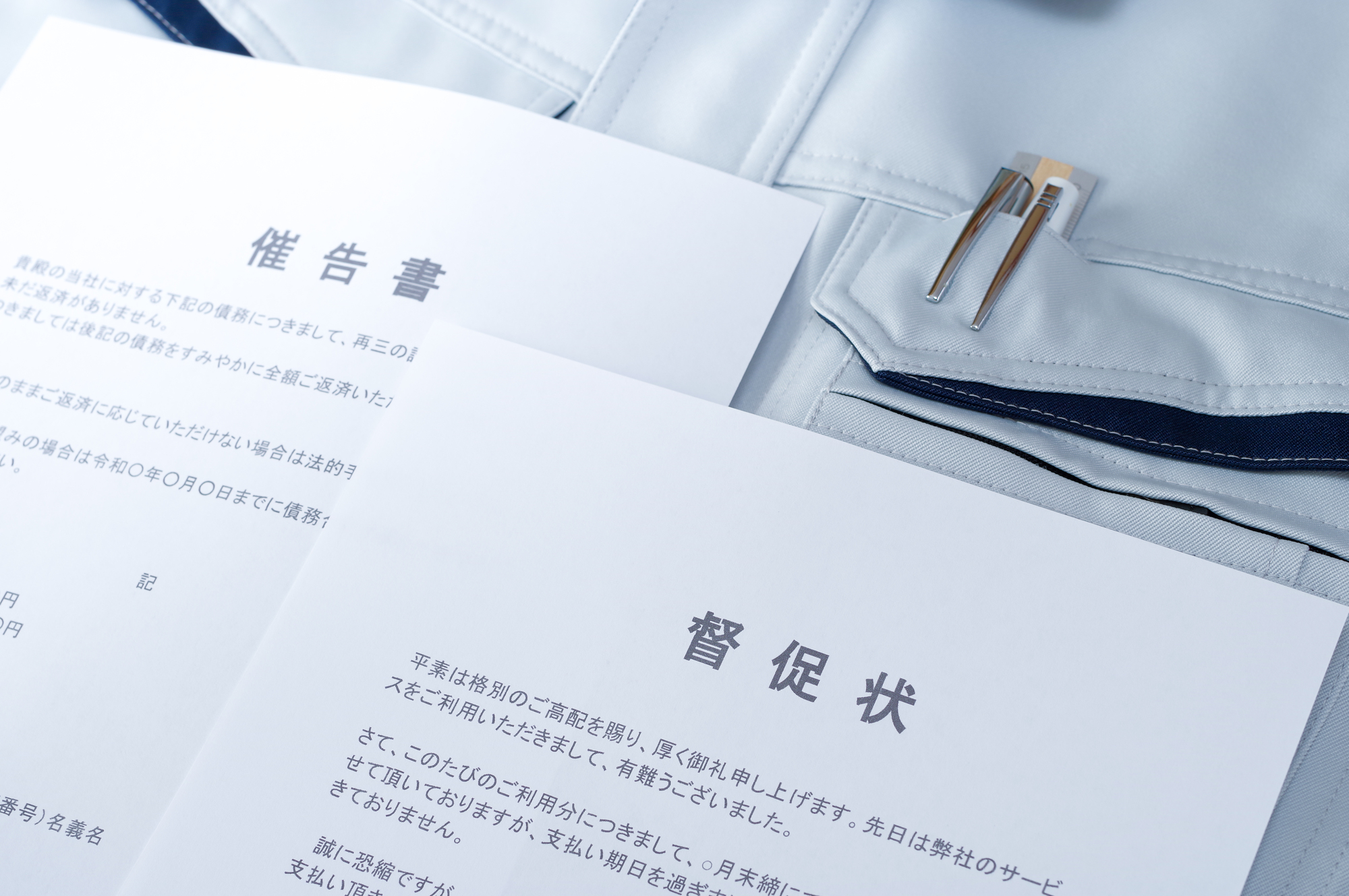
医療機関は未収金が発生した場合、きちんと対処して回収する必要があります。ここでは、具体的な回収方法として、初期の督促から法的手段までを段階的にチェックしていきましょう。
未収金を放置すると回収が困難になって経営に影響しかねないため、速やかに対処することが大切です。
電話や文書で督促する
医療費の未収金が発生した際、最初にやることは督促です。単純に支払いを忘れていたり請求書を見落としていたりする場合は、電話や文書で督促すればすぐに支払ってもらえることが多いでしょう。
数回督促しても反応がない場合や支払いを拒否された場合は、内容証明郵便での督促を検討します。内容証明郵便は、いつ、どのような内容で督促したかが残るため、将来的な法的対応の際にも有効です。この段階では、法的措置への移行可能性も含めて記載し、期日までに支払うように促しましょう。
一部納付・分割払いを提案する
医療費の一括支払いが困難な患者に対しては、分割払いを提案するのが有効です。患者と話し合って無理のない支払い計画を立てましょう。
分割払いを設定する際は、まず月々の支払い可能額を算出します。支払回数や支払額が決まったら、支払い計画書を作成して明文化することが大切です。
支払い計画書には、支払総額・分割回数・月々の支払額・各回の支払期日などを明記します。また、支払いが滞った場合の対応についても事前に取り決めておくことで、トラブルを回避できるでしょう。
保険者に請求する
未収金を回収する際に覚えておきたいことのひとつが、国民健康保険法第42条に基づく健康保険の強制徴収制度です。これは患者が医療費を支払わない場合、保険者(保険組合等)が医療機関に代わって未払い分を徴収してくれる制度を指します。
ただし、この制度を利用するには定められた要件を満たさなければいけません。保険者への請求を検討する場合、保険者が定める条件を満たすように、書面や訪問できちんと督促を行うなど、回収努力を尽くしましょう。
督促記録の適切な保管や患者との交渉経過の文書化など、後の請求に備えた準備も必要です。
法的措置で回収する
電話や内容証明郵便での督促を重ねても医療費の支払いが得られない場合は、法的措置による回収を検討しましょう。
法的措置のひとつが支払督促で、簡易裁判所に申し立てれば裁判所から患者に督促してもらえます。支払督促は書類の提出のみで利用でき、裁判所への出頭や証拠書類の提出は必要ありません。
裁判所に納める手数料も訴訟の半額で済み、1,000,000円の請求なら5,000円で申し立て可能です。患者から異議申し立てがなければ仮執行宣言付支払督促が発付され、強制執行を申し立てられます。
ほかにも、小額訴訟(訴額600,000円以下に限る)や通常訴訟を検討してもよいでしょう。どの法的手段を選ぶとよいかは請求額や患者の対応によって異なるため、弁護士への相談も含めて慎重に判断することが重要です。
医療費の未収金を予防するための対策

医療費の未収金対策において効果的なのは、未収金が発生しないように予防策を講じることです。事前に対策することで回収にかかる時間やコストを削減し、本来の医療サービスに集中できる環境を整えられます。
ここでは、保険資格の確認強化や預かり金制度の活用、定期的な精算システムの導入など、効果的な予防策について詳しく解説します。
保険資格の事前確認を徹底する
保険資格の事前確認は、医療費未収金を防ぐ基本的かつ重要な対策です。患者が受診時にマイナンバーカードや資格確認書を提示できない場合、未収金リスクを抱えることになります。
継続的な通院でも、毎月の保険資格確認を徹底することが大切です。オンライン資格確認システムもあるため、マイナンバーカードを活用して最新の保険資格情報をすぐに確認できます。
保険資格を確認できない場合は、一旦医療費全額の支払いを求めて後日精算するルールにすることで、未収金リスクを大幅に軽減できます。
預かり金制度を導入する
患者が入院したり高額な治療を受けたりする際に、事前に一定額を医療機関に預けてもらう仕組みを導入すれば、未収金リスクを低減できます。預かり金の額は、想定される治療費や入院費を考慮して決めるとよいでしょう。
万が一未収金が発生しても、預かり金から充当できます。ただし、預かり金制度を導入する際は、患者への十分な説明が欠かせません。預かり金が必要な理由や適切に支払いが行われればきちんと返金されることなどを説明し、理解を得ることが大切です。
入院費を定期的に精算する
入院期間が長期化すると医療費が高額になり、負担が大きくなります。請求が高額になると支払えずに未収金になるリスクが高まるため、入院が長期化する場合は月1回請求するなど定期的に医療費を精算できるようにしましょう。
例えば、月末締め翌月10日支払いのようにあらかじめスケジュールを決めておくのがおすすめです。定期的に精算することで、退院時の一括請求額が高額になることを防げます。
患者にとっても、毎月の支払額を把握しやすくなり、計画的な資金準備が可能です。限度額適用認定証を活用すれば月ごとの自己負担限度額を超えた分は支払う必要がないため、経済的負担がさらに軽減されます。
医業未収金補償保険に加入する
医業未収金補償保険は、医療費の未収金を補償する医療機関向けの保険制度です。日本病院会会員向けに提供されていて、未収金が発生してから90日経過すると保険金を受け取れます。
対象は外国人患者限定プランと全患者プランがあり、医療機関のニーズに応じて選択可能です。多くの患者を診察する上で未収金の発生そのものを防ぐのが難しいことを考えると、保険加入は有効な対策といえるでしょう。
医療費の未収金対策には決済手段の多様化が効果的

現金以外の決済手段を充実させることも、未収金対策として効果的です。患者が支払い方法を選べるようにすることで、手持ちの現金不足による未払いを防ぎつつ、支払いの利便性を高められます。
ここでは、医療費の支払いに利用される決済手段を見ていきましょう。それぞれの仕組みとメリットを知って適切に組み合わせることで、医療機関の未収金リスクを大幅に軽減できます。
口座振替
口座振替は、事前に銀行口座を登録することで、指定した日付に自動で診療費が引き落とされる仕組みです。
現金が必要なく、自動引き落としにより未収金リスクが低減できます。診察ごとに支払いを行う手間が生じないため、定期的な通院が必要な慢性疾患の患者にもおすすめです。
コンビニ決済
コンビニ決済は、発行された「払込票」をコンビニ店頭などに持参し、支払う方法です。銀行口座やクレジットカードの登録が不要で、店頭での現金支払いが基本のため、手軽さを求める方に適しています。
また、コンビニ決済はコンビニの営業時間内であれば、24時間365日支払いが可能な点が魅力。窓口支払いと違い、患者の都合のよいタイミングで支払えるため、回収率アップが期待できます。
払込票のバーコードをスマホアプリで読み込んで支払いを行う「スマホ決済」に対応しているサービスであれば、店頭に足を運ばずに自宅からでも支払いが可能になり、より便利です。
クレジットカード決済
クレジットカード決済では、事前にクレジットカードを登録して支払いを行います。分割払いやリボ払いが選択できるので、診療費が高額になったとき、一時的に負担を軽減できる点が特徴です。カード会社によっては、支払い額に応じてポイントが貯まります。
ただし、クレジットカードを持っていない方は利用できないため、カード所持率が低い若年層や高齢者層が多い医療機関では、その他の決済手段との併用を検討するとよいでしょう。
医療機関の未収金へ対策するならリコーリースへ!

医療費の未収金対策を検討しているなら、ぜひリコーリースをご検討ください。リコーリースでは、口座振替とコンビニ決済の2つの決済手段に対応した集金代行サービスを提供しています。コストの適正化やスムーズな運用体制の構築など、医療機関のニーズに応える機能を備えているのが特徴です。
ここでは、医療機関にとってリコーリースの集金代行サービスがおすすめといえる理由を見ていきましょう。
初期費用無料で導入できる
リコーリースの集金代行サービスは、初期費用0円で導入できるため、医療機関のコスト負担を抑えられます。提供している決済手段は、口座振替とコンビニ決済の2つ。管理に使用する専用Webサイトも無償提供されるため、インターネットに接続できるPCがあれば、すぐにサービスを利用可能です。
利用しなかった月は基本料金が発生しないのも、リコーリースのメリットといえるでしょう。患者数の変動が大きい場合でも導入しやすい料金体系です。
請求件数が少なくてもリーズナブルに利用できる
リコーリースの集金代行サービスは請求件数1件から利用可能で、小規模な医療機関でも導入しやすいのが魅力です。開業したばかりのクリニックや、新規事業として在宅医療を始めた医療機関など、まだ患者数が少ない段階でも無理なく活用できます。
コストを適正化しつつ集金代行サービスを利用したい方は、ぜひリコーリースをご検討ください。
導入前後のサポートが充実している
導入前の丁寧なヒアリングから導入後の運用サポートまで、一貫した支援体制が整っているのもリコーリースの集金代行サービスのメリットです。
導入検討時には各医療機関の状況を詳しく確認し、適切なプラン・決済方法を提案します。導入後は専用のフリーダイヤルを完備し、操作方法や不明点があるときはすぐに相談できるため安心です。
また、定期的に利用状況を確認し、必要に応じて運用方法の見直しも行っています。医療機関の成長や変化に合わせて柔軟に対応できるのがリコーリースの魅力です。
「見積依頼」も素早く対応!
お気軽にご相談ください
まとめ
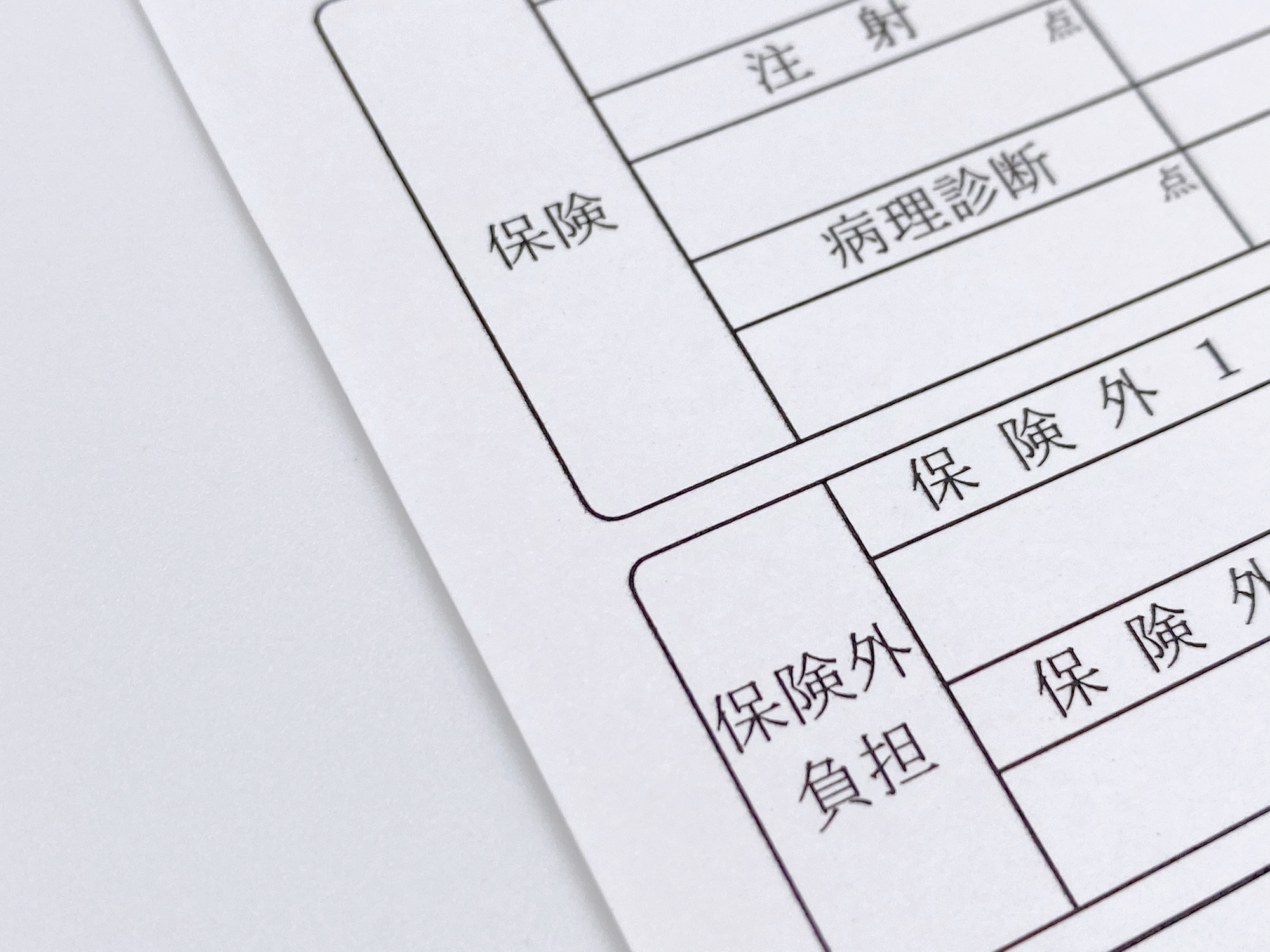
医療費の未収金は、医療機関の経営悪化を招く原因のひとつです。主な発生原因には、緊急入院時の所持金不足や患者の経済的困窮、外国人患者による未納があります。
事前に主な原因を知って予防策を講じれば、未収金リスクを大幅に低減できるでしょう。集金代行サービスの導入によって決済手段を多様化するのも、未収金対策として効果的です。
これから決済手段の多様化を進めようと考えているなら、初期費用0円で導入しやすく、サポートも充実しているリコーリースの集金代行サービスをぜひご検討ください。

【監修】尾﨑 宗則 リコーリース株式会社 BPO本部長
1999年リコーリース株式会社に入社。
情報システム部や事業統括部門、営業部門の支社長、子会社(テクノレント社)の営業統括本部長など、重要なポストを歴任した後、2025年4月~決済サービスを管轄するBPO本部長に就任。
数々の商品企画やシステム開発に携わり、豊富な経験と実績・幅広い分野の知識を有するゼネラリスト。